ポリアミンとは?その効果や多く含まれる食品を徹底解説
 高尾 浩一
高尾 浩一
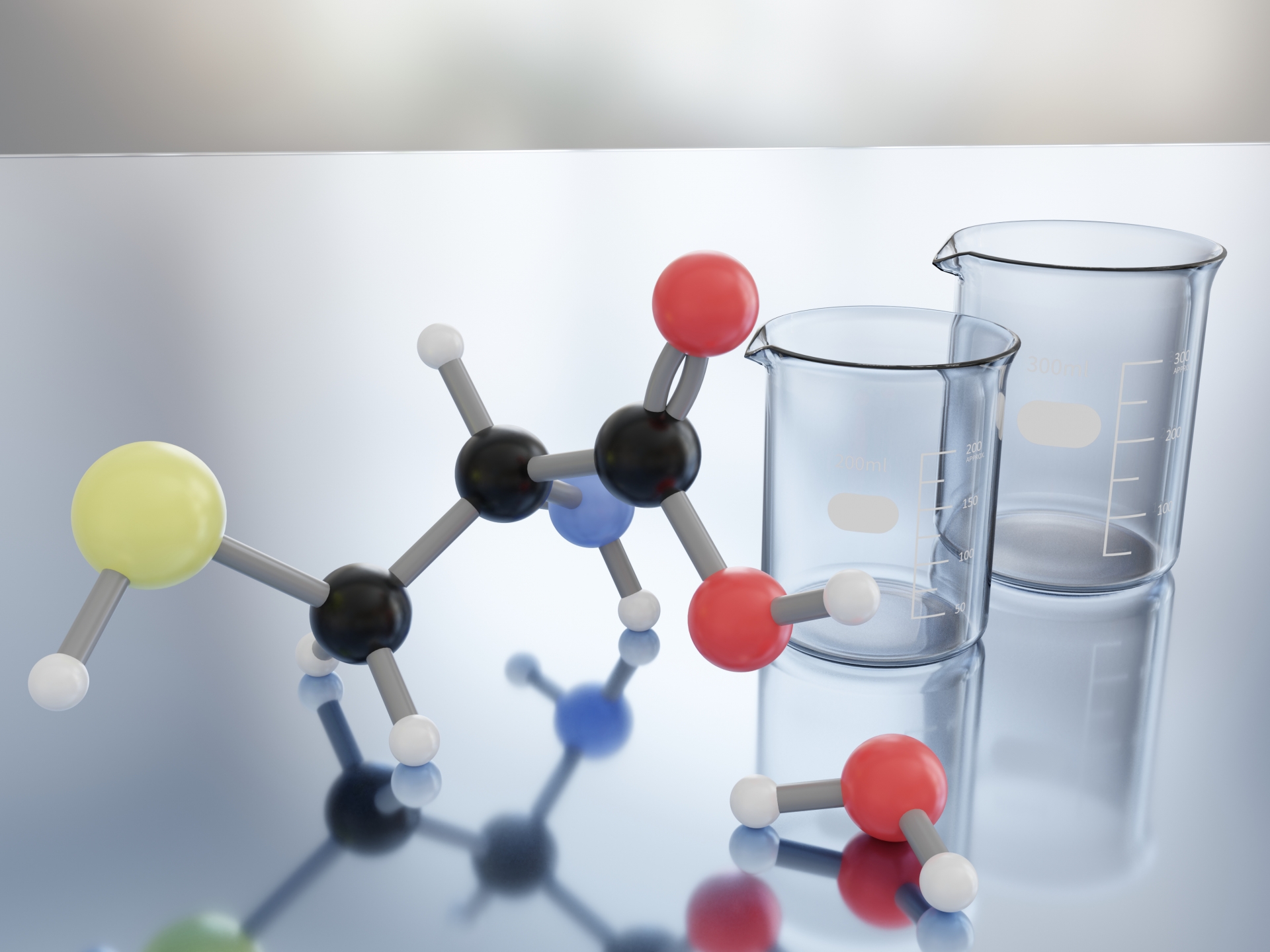
私たちの体は常に細胞分裂を繰り返しながら成長していきますが、これを支える物質のひとつに「ポリアミン」と呼ばれるものがあります。
一般的には聞き慣れない物質であり、はじめて知ったという方も多いと思いますが、健康維持や老化防止のために重要な役割を果たしています。
本記事では、ポリアミンとはどういった物質なのか、主な働きや摂取方法、ポリアミンに関する最近の研究なども合わせてご紹介します。
もくじ
ポリアミンとは

はじめに、ポリアミンとはどういった物質なのか、主な種類についても解説します。
ポリアミン
ポリアミンとは、体内のあらゆる細胞の中で生成される物質です。
細胞分裂や細胞増殖を促進するなど重要な役割を果たすことから、ヒトを含む生物にとって欠かせない成分とされています。
また、ポリアミンは細胞内でDNAやタンパク質と結合し、分子の構造や機能を安定化させる働きがあることも分かっています。
このように、ポリアミンは生命活動の基本的なプロセスに深く関与しており、健康維持はもちろんのこと老化防止の鍵を握る物質としても注目されています。
主な種類と特徴
一口にポリアミンといってもいくつかの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
代表的なポリアミンにはプトレシン、スペルミジン、スペルミンの3種類が存在します。
- プトレシン:厳密にはポリアミンではないのですが、ポリアミンの原料になるので含めることが多い アミノ酸の一種であるオルニチンから生成される
- スペルミジン:プトレシンから作られるポリアミンで、eIF5Aの機能発現に必須 オートファジー(細胞内のタンパク質を分解する働き)を促進する
- スペルミン:スペルミジンから作られるポリアミンで、活性酸素から細胞を保護したり、DNA情報の転写・翻訳を促進する
これらは体内のいたるところに存在していますが、細胞内の濃度や分布が厳密に調節されています。
そのため、ポリアミンが過剰になったり、不足したりすることによって、さまざまな病気の原因となる可能性があります。
体内での生合成と分布
ポリアミンは主に体内で生成されますが、食事からも摂取することができます。
体内では、アミノ酸の一種であるオルニチンとメチオニンをもとに、酵素の働きによってプトレシン、スペルミジン、スペルミンが順次合成されます。
ポリアミンは体内のあらゆる細胞内で生成されますが、特に腸管など細胞の増殖が盛んな組織に多く分布している傾向が見られます。
また、ポリアミンの分布は年齢や健康状態によっても変化し、加齢にともないその濃度が低下することも分かっています。
そのため、健康維持や老化予防においてはポリアミンを適切に補給することが重要視されています。
関連記事:BCAA(分岐鎖アミノ酸)の効果とは?EAAとの違いを解説!
ポリアミンの働き

ポリアミンは体内でどのような効果をもたらすのでしょうか。主な4つの働きについて分かりやすく解説します。
細胞の成長と増殖への影響
ポリアミンは細胞が成長したり、増殖したりするために欠かせない成分です。
そもそも、細胞が分裂する際にはDNAやタンパク質の合成が必要ですが、ポリアミンはこれらの分子を安定化したり合成を促進したりする役割を果たします。
特にスペルミジンやスペルミンは、細胞が分裂するタイミングを調節するなど、スムーズに細胞増殖が進行するようサポートする役割を果たしており、傷ついた組織の修復や新しい細胞の生成に不可欠な存在です。
抗炎症作用と抗酸化作用
ポリアミンには抗酸化作用と抗炎症作用もあり、正常な免疫機能の維持や体内の酸化ストレスの軽減にも寄与します。
具体的には、スペルミジンやスペルミンが活性酸素を中和することで、細胞膜やDNAへの損傷を防ぎます。また、炎症反応を調節することで慢性疾患の予防にも効果が期待されています。
オートファジーの促進
オートファジーとは、細胞内の不要物や損傷した細胞を分解・再利用するプロセスのことで、ポリアミンにはこれを促進する働きもあります。
特にスペルミジンはオートファジー活性を高める働きがあり、細胞の健康を維持し、神経疾患やがんの予防にもつながる可能性があると考えられています。
老化防止と寿命延長の可能性
わたしたちの体は常に細胞分裂を繰り返していますが、老化とともに細胞の代謝が衰えていきます。
その結果、本来であれば除去されるべき老化細胞が体内に残り続け、それが原因で臓器や組織の機能低下やさまざまな疾患の発症原因にもなります。
ポリアミンは細胞の成長や分裂を促進することで、老化防止や寿命延長にも寄与する可能性があります。
ポリアミンを多く含む食品

ポリアミンは加齢とともに減少していくため、食品から摂取することが求められます。
ポリアミンが多く含まれる食品には、主に発酵食品や大豆食品、きのこ類、魚介類、ナッツ類などがあります。
- 発酵食品:味噌、チーズ、ぬか漬け など
- 大豆食品:豆腐、納豆 など
- きのこ類:しいたけ、マッシュルーム、しめじ など
- 魚介類:牡蠣、うなぎ など
- ナッツ類:アーモンド、ピーナツ、ピスタチオ など
効率的なポリアミンの摂取方法
加齢とともに減少するポリアミンを補うためにどのような方法が効果的なのか、摂取する際の注意点も解説します。
食事からの摂取
ポリアミンを効率的に摂取するには、食品から取り入れることが基本です。
上記で紹介した発酵食品や大豆食品、きのこ類、魚介類、ナッツ類などを適度に取り入れ、栄養バランスのとれた食事を心がけると良いでしょう。
サプリメントの活用
食事だけで摂取することが難しい場合、ポリアミンを含むサプリメントの活用も一つの選択肢です。
サプリメントはポリアミンを効率的に摂取できるよう開発されていますが、一口にサプリメントといってもさまざまな製品があるため、信頼性が高く安全性も担保された商品を選ぶことが重要です。
関連記事:健康食品の定義とは|選ぶ際の目印や注意すべきポイントについて
ポリアミンに関する最近の研究

ポリアミンがもたらす効果やメカニズムはすべてが解明されているわけではありませんが、近年の研究によって新たに分かってきたこともあります。
健康維持への効果
ポリアミンを多く含む食品を摂取することが、腸内環境の改善や免疫機能の向上に寄与する可能性が報告されているほか、腸内細菌との相互作用により代謝のバランスに影響を及ぼす点も注目されています。
また、ポリアミンは血圧の調節や心血管系疾患(心筋梗塞・脳梗塞・心不全・狭心症など)のリスク低減にも関与し、長期的な健康の維持に役立つと考えられています。
老化防止のメカニズム
ポリアミンが老化を遅らせるメカニズムについての研究も急速に進んでいます。
具体的には、スペルミジンが細胞の代謝を活性化させることが老化防止の重要な鍵を握っているとされており、老化に伴う細胞の損傷や機能低下が抑えられるほか、さまざまな組織の機能改善や疾患の抑制にもつながります。
今後の研究課題
ポリアミンは過剰摂取の心配や副作用のリスクが低く、摂取後に体内で吸収されやすい物質と言われています。
ただし、がんを患っている場合には、ポリアミンによって腫瘍の成長を促すという報告もあるため、これを解決するための研究は今後の課題となります。
また、ポリアミンはタンパク質の生成を促す作用があることから、薄毛治療やアンチエイジング、損傷した関節の治療といった分野にも広く応用が期待されています。
ポリアミン摂取時の注意事項
食事やサプリメントからポリアミンを摂取する際にはどういった点に注意すべきなのでしょうか。
過剰摂取のリスク
ポリアミンそのものの摂取上限量は特に定められていませんが、摂取量を増やそうとするあまり、食事のバランスが偏ってしまうことで、塩分や脂肪分、糖分などの過剰摂取につながるおそれもあります。
そのため、バランスのとれた食生活を心がけ、サプリメントは補助的な役割として活用するのが理想的といえるでしょう。
サプリメントによっては1日の摂取量の目安が記載されている製品もあるため、パッケージや説明書に記載された用量を守りましょう。
特定の疾患を持つ方への影響
今後の研究課題の中でも述べた通り、がんを患っている方がポリアミンを摂取した場合、腫瘍の成長を促し重症化するリスクがあるといわれています。
がん以外にも何らかの疾患を持つ方や、妊娠中・授乳中の方でサプリメントを摂取する場合には、健康上のリスクがないかを事前に医師に相談しておきましょう。
まとめ
ポリアミンは私たちの体内で生成される物質のひとつであり、細胞の成長や増殖のために重要な役割を果たしています。
しかし、加齢とともにポリアミンの量は減っていき、老化を招いたり病気を発症する要因とされています。
そのため、健康的で若々しい体を維持していくためにも、ポリアミンが多く含まれる発酵食品や大豆食品などをバランス良く食事に取り入れてみましょう。
ポリアミンは副作用のリスクは低いとされていますが、がんを患っている方が摂取すると腫瘍の成長を促進し、重症化を招く可能性があることも近年の研究で明らかになっています。
そのため、病気の治療中または疑いがある方がポリアミンを摂取する場合には、あらかじめ医師に相談することが大切です。

高尾 浩一
- 所属:薬学部 薬科学科(生体分析学講座/研究室)
- 職名:教授
- 研究分野:ライフサイエンス / 分析化学 / 生化学
- 研究課題:生体アミン(モノアミン、ジアミン、ポリアミン)に関する研究
・各種疾患モデルにおけるポリアミン代謝酵素活性変動追跡と阻害剤を用いた治療薬開発
・脳虚血再灌流障害モデルを用いたスペルミン酸化酵素阻害剤の応用
・蛍光誘導体化による新規ポリアミン測定法の開発
・生体アミン酸化酵素に対する阻害剤の開発
・生物界に存在する多様なポリアミンの合成法と分析法の開発
学位
- 博士 (薬学)( 1999年03月 城西大学)




