化学実験の原風景

化学の実験と聞くと、試験管を振りながらその中身を見つめる科学者という漫画のようなイメージを思い浮かべる方も多いでしょう。これは、あながち無根拠なものでもなく、ある化学実験では実際によく見かける光景でもあります。私たち日本人は、なぜこのような光景を化学実験の原風景としてイメージするのでしょうか。
そもそも「化学」とは

まずは、より具体的に化学実験とは何なのかを考えてみましょう。
たとえば、中学校の理科の授業でマグネシウムに火をつけると花火のように光りながら燃焼するという実験をしたことはないでしょうか。また、過酸化水素水に二酸化マンガンを加えることでポコポコと発生する酸素を、水上置換法によって集める実験をした記憶はないでしょうか。
これらのように、物質が何か別のものへと変化する現象を化学反応とよびます。そして、化学反応を中心として物質の性質や構造を解き明かそうというのが「物質の変化の学問」、すなわち「化学」です。
日本に化学が輸入されたのは
化学は西洋で誕生し発達した学問ですが、日本に化学が初めて体系的に導入されたのは江戸時代後期といわれています。1837年から1847年にかけて、蘭学者である宇田川榕菴がオランダの化学書を翻訳し、『舎密開宗』という本を発行したのが始まりとされています。
当時、前野良沢および杉田玄白らが、オランダの医学書を翻訳して『解体新書』として発表し西洋医学を紹介したことはよく知られていますが、化学においても同様のことを宇田川榕菴が行っていたのです。
ちなみに、当時、西洋の学問を学ぶためには日本と唯一国交のあったオランダを経由してさまざまな情報を集めなければなりませんでした。宇田川榕菴が翻訳した『舎密開宗』の「舎密」とは、オランダ語で化学を意味する「chemie(セイミ)」に漢字を当てたものであり、つまり榕菴の作った言葉なのです。
そこに「開宗=新たに宗派をたてる」という言葉がついているため、日本に新たな学問として「舎密=化学」を紹介したいという榕菴の強い意志が感じとれます。
日本における化学実験のはじまり

宇田川榕菴はこの『舎密開宗』の中で様々な化学用語を翻訳しています。そのなかには「酸素」や「水素」、「酸化」や「還元」などのように、そのまま日本語として定着して現在も使用されているものも多くあります。それと同時に、さまざまな化学実験も紹介しています。
そのうちの一つに、温泉中に含まれる化学物質(陽イオンや陰イオン)を調べる実験がありました。榕菴は実際に熱海や有馬など全国各地の温泉地へ趣き、温泉の分析も行ったそうです。
サンプル中に含まれている化学物質を明らかにする分析は「定性分析」とよばれ、当時の西洋で急速に進歩・体系化が行われていました。榕菴はいち早くその成果を日本に紹介したことになります。
水中に含まれる銅や鉄などの金属イオンの定性分析は、幕末を迎え急速な西洋化を志向していた日本ではその必要性が広く認識され、『舎密開宗』以上の詳細な情報が必要とされました。
そこで、1856年、蘭学者である河野禎造は、最新の金属イオンの定性分析手法を翻訳し『舎密便覧』という本にまとめました。この本の中では、金属イオンを含む溶液に化学薬品を加えたときに、金属イオンごとに異なる色が沈殿する様子をカラーで紹介しています。
原風景として定着した「金属イオンの定性分析実験」
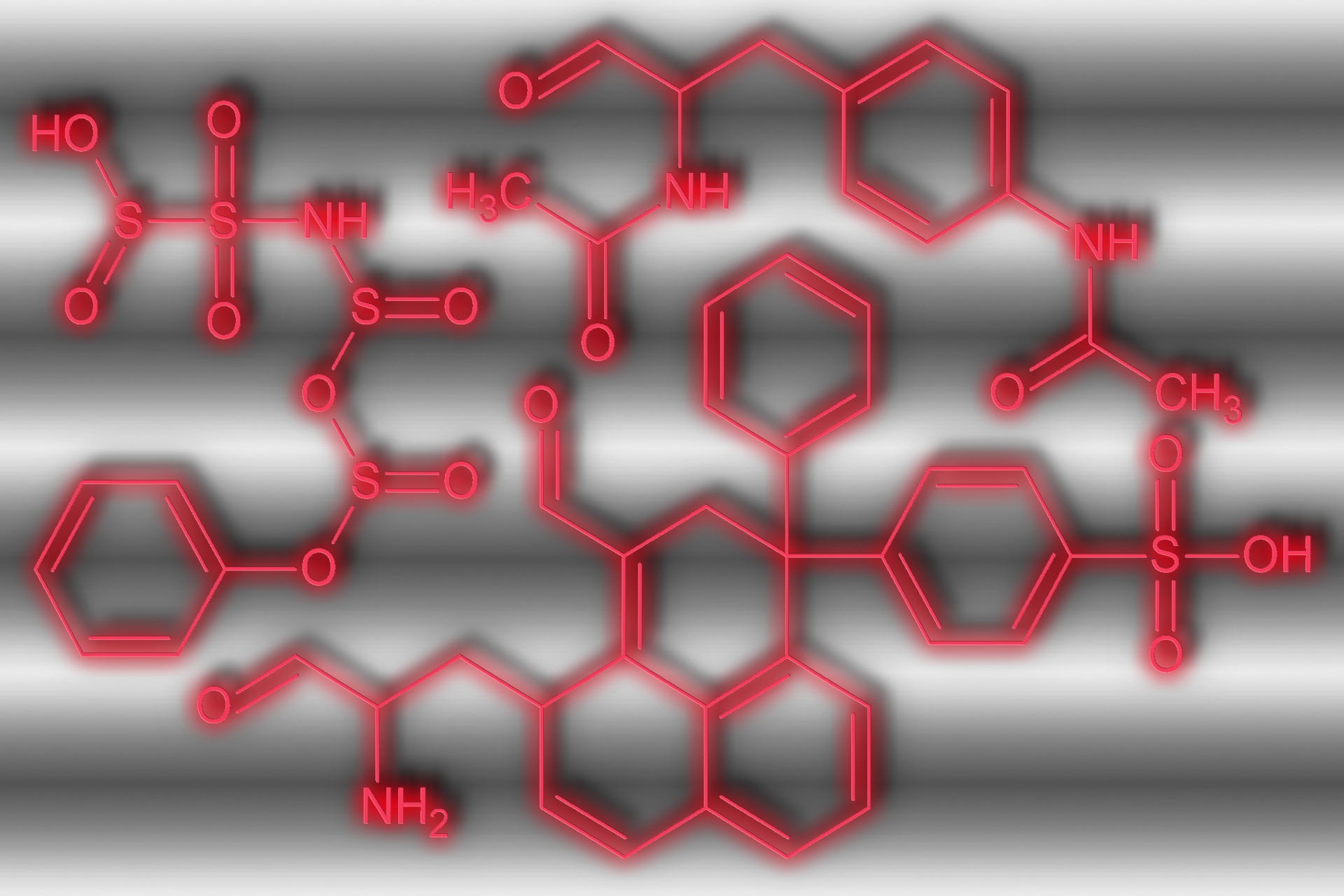
この『舎密便覧』以外にも、さまざまなルートで日本に導入された金属イオンの定性分析実験は、またたく間に日本中に広まり、西洋化に欠かせないものとなりました。
つまり、試験管に化学薬品を加えて、よく振り混ぜて鮮やかな色の沈殿を出す金属イオンの定性分析のことを、多くの日本人は化学実験だと認識するようになり、冒頭で挙げた典型的化学実験の原風景として定着していったと考えられるのです。
この金属イオンの定性分析は、1840年頃にドイツのカール・フレゼニウスが系統的にまとめ上げたことで一応の完成をみました。
その後、この実験を学校教育に活用しようと考えたのが、フレゼニウスの元上司であったドイツ・ギーセン大学のユストゥス・フォン・リービッヒであり、化学教育カリキュラムを確立した最初の人物とされています。
リービッヒは学生が一斉に同じ実験を行い、実験を通して学ぶ教育法を最初に実践しました。このリービッヒの教育法は全世界の大学化学教育の模範となり、そこで行われた金属イオンの定性分析実験は世界中の大学で標準プログラムとして組み込まれていったのです。
現在もその教育法は引き継がれており、城西大学理学部化学科においても金属イオンの定性分析実験は2年生必修科目の基礎化学実験として行われています。
本学に限らず、大学で化学を学ぶ学生は必ずこの実験を行っているほか、化学分析に関する国家資格である「化学分析技能士」では金属イオンの定性分析が実技試験の対象科目となっています。
多種多様な化学薬品を使用し、化学者に欠かせない繊細な実験操作と、注意深い観察眼が養われるこの実験は極めて高い教育効果が得られるとされているためです。
ここまでの内容をまとめると、日本人にとっての化学の原風景は「金属イオンの定性分析」であり、その背景には江戸時代後期から西洋化に移り変わるなかで欠かせないものであったこと、そして大学化学教育のカリキュラムとして採用されたことが大きく関連しています。
しかし、それだけでなく、この原風景をわかりやすい絵や映像などで示し、世に広めた人が必ずいたはずです。そうでなければ、今もなお多くの人が化学実験についてこれほど画一的なイメージをもつとは思えません。
それは一体誰なのでしょうか。私自身は、手塚治虫なのではないかと考えているのですが、これを証明するには彼の全作品を検証しなければなりません。
参考文献
『現代化学 原子・分子の科学の発展』 廣田襄 (京都大学学術出版会, 2013)
『日本の化学の開拓者たち』 芝哲夫 (裳華房, 2006)
『日本の化学を切り拓いた先駆者たち(1) : 宇田川榕菴と舎密開宗』 芝哲夫, 化学と教育, 2003, 10, 638-640.
『日本の化学を切り拓いた先駆者たち(3) : 河野禎造と舎密便覧』 芝哲夫, 化学と教育, 2003, 51, 797-799.
『無機半微量分析 第2版』 松浦二郎, 西川勝, 栗村芳實(東京化学同人,1978)
『系統的定性分析と周期表』 阿部重喜, 化学教育, 1974, 22, 419-421.
『幕末ロンドンにおける薩長留学生と化学の出会い』 菊池好行, 理科通信サイエンスネット, 2015, 53, 6-9.

宇和田 貴之
・城西大学 理学部化学科 准教授
・博士(工学)(大阪大学)


